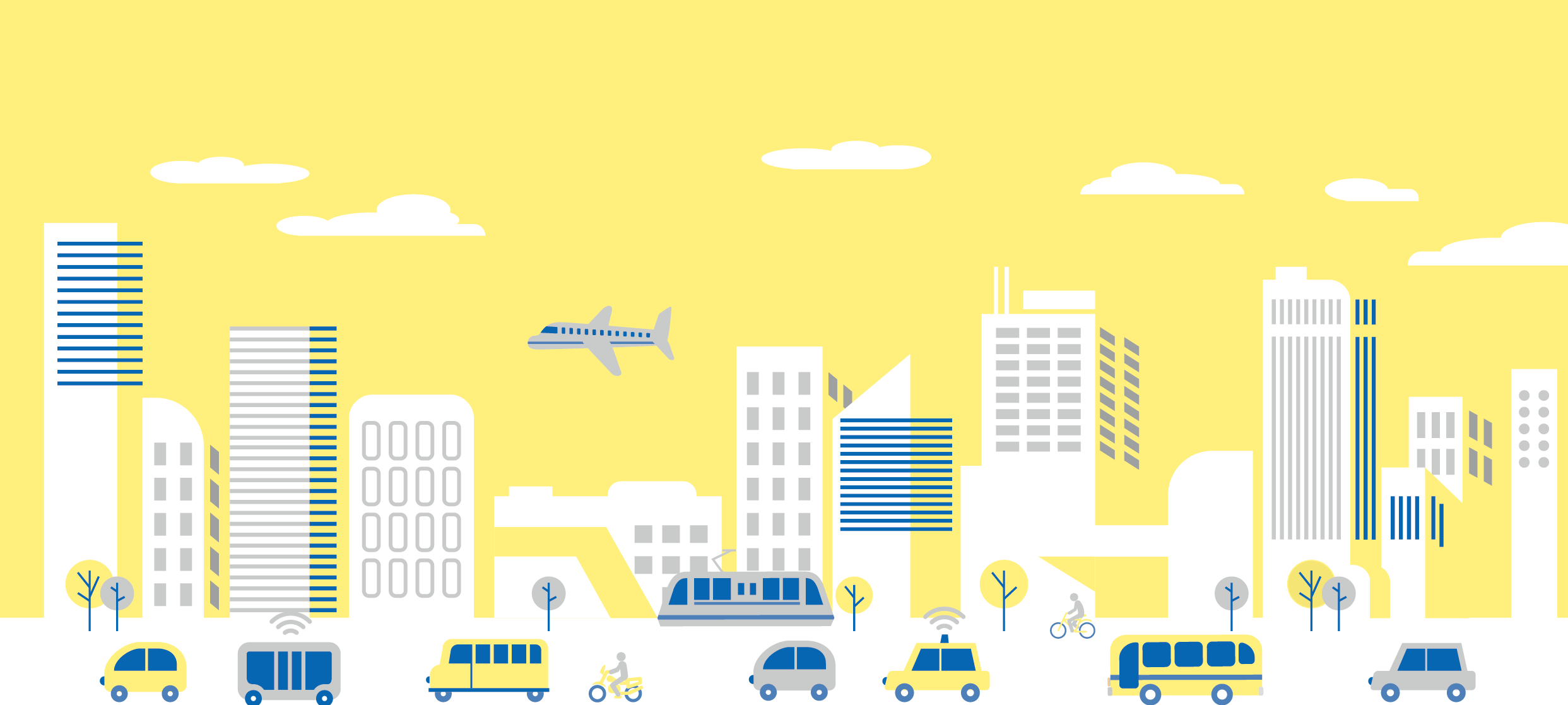モビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)にかかわる教員支援制度
1.事業の目的及び概要
モビリティ・マネジメント教育とは
「モビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)」とは、私たち一人ひとりの移動手段や社会全体の交通を「人や社会、環境にやさしい」という観点から見直し、改善していくために自発的な行動を取れるような人間を育てる(力を育む)ことを目指した教育活動を指します。具体的には、例えば、以下のような学習を意味します。
- 地域の電車・バスなど(公共交通)について考える学習
- クルマ社会の問題(渋滞・環境問題など)について考える学習
- まちづくりと交通について考える学習
- 交通を通じて自分たちの住む地域やふるさとについて考える学習
- その他、まち・環境・公共(政治や公民的資質、シティズンシップなど)と交通に関わる、様々な学習
詳細につきましては、「モビリティ・マネジメント教育とは」や「モビリティマネジメント教育のすすめ」 のページをご確認ください。
事業の目的
これまで交通エコロジー・モビリティ財団(以下、「エコモ財団」という)では、モビリティ・マネジメント教育の普及を目指し、 これまで14自治体に対し、ノウハウの提供や資金面での支援を行うほか、平成22年度から学校への直接支援を行い、 継続的に実施するための拠点づくりに取り組んできました(のべ158件)。また学識経験者、関係団体等と連携し、教員向けの普及ツールとして、 「モビリティ・マネジメント教育のすすめ」の作成や書籍「モビリティ・マネジメント教育」の発行、メールマガジンの配信、ポータルサイトの運営などを行っています。
令和7年度も、モビリティ・マネジメント教育の実施に意欲的な教員に対して、ノウハウの提供や資金面での支援を行い、 実施校の拡大と新たな教材事例の増加を図ることを目的として本制度を実施します。
2.支援内容
エコモ財団は以下のことを通じて、モビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)の実施に係わるノウハウの提供や資金面での支援等を行います。
(1)実施面での支援
- 当該地域の自治体や交通事業者などと連携の支援
- 過去に支援した自治体や教員との連携の支援
- 教材や参考となるデータの提供などの支援(国内外の交通に関わる取り組み事例の情報提供等)
(2)資金面での支援
-
支援対象経費
鉄道・バス利用等の学習の実施にかかる費用(講師謝金(外部の方に講演を依頼した場合)、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、図書資料等の購入費)
-
支援限度額
1校につき、15万円程度を限度として協議の上定めます。
※ただし、要望があった場合は、5万円を限度として追加支援を認める場合があります。
【追加支援の判断基準】
支援金の使途が適切であり、「5(2).選定基準」を全て満たしたうえで、以下のいずれかに該当するもの。
a.行政機関や交通事業者、地域、NPOなど多様な関係機関との連携が意図されているもの。
b.学会や研究会など、対外的に取り組み事例等の発表を行う場合。(令和7年度に実施した取り組みの発表が翌年度になる場合は、様式1の支援申請書に翌年度を含む実施計画を記載してください。2年間の継続支援として認めることがあります。)
注意事項:本支援制度の対象となるのは、支援決定後からの取組となります。決定前の支出は対象となりませんので、ご注意ください。
(3)支援期間
原則単年度限りとします。
3.申請資格
本事業の申請者は小中高等学校の教員または、教員による研究グループとします。ただし申請にあたっては、校長の承認を得られていることを前提とします。
4.応募の方法等について
(1) 応募書類の書式(応募様式)について
応募書類は次の2種類です。なお、下記様式1については必須とします。
- 令和7年度交通環境学習にかかわる教員支援制度 支援申請書【様式1】
- 補足説明資料【様式自由】(必要に応じて提出)
(2) 提出方法
郵送での提出を厳守とします。なお、提出いただいた申請書類一式は返却いたしません。
(3) 提出先
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル10階
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 企画調査部 田中宛
(4) 募集期間
令和7年6月14日(当日消印有効)
詳細につきましては募集要項をご参照下さい。
5.選定方法
(1)選定方法
応募案件は、学識経験者や国土交通省等の関係者で構成される「モビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)普及検討委員会」において審査、選定されます(7、8月開催予定)。書面による審査を基本としますが、必要に応じて電話での問い合わせをさせていただくこともあります。
(2) 選定基準
- 実施内容の適合性
実施する学習の内容が、運輸・交通部門の環境問題を題材とした学習(交通環境学習)となっているか。
- 実施計画の妥当性
教科等の学習の単元で実施される場合は、当該単元との整合性が図られているか。また、実施時期や実施字数が無理なく計画されているか。
- 地域の交通との関連性
児童や生徒が取組みやすいように、当該地域での交通を題材とした計画が立てられているか。
- 他校への波及性
他校でも取組めるような内容になっているか。
- 学習の持続可能性
支援終了後も継続して実施できる内容となっているか。
(3)結果通知
選定結果は、応募者宛に文書で通知します。合わせて、支援校の名称及び学習の概要を本ポータルサイトなどで公表します。
6.その他
支援事業の実施状況や事業完了報告書等は、エコモ財団に帰属するものとし、モビリティ・マネジメント教育の普及のためにホームページ等で公表します。
7.実施スケジュール
| 令和7年 6月14日 | 申請締切(当日消印有効) | |
|---|---|---|
| 令和7年 7、8月 | 委員会において審査の上、支援校を選定 | |
| 令和7年 8月 | 支援開始(予定) | |
| 令和8年 3月24日 | 実施期間終了 | |
| 令和8年 3月26日 | 事業完了報告書等の提出 | |
8.応募書類等
案内 |
募集要項 |
|
|---|---|---|
支援申請書【様式1】 |
||
請書【様式2】 |
||
振込先通知書【様式3】 |
||
完了報告書【様式4】 |
||
内訳精算書【様式5】 |
||
辞退届【様式6】 |
9.モビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)普及検討委員会 委員名簿
| 委員長 | 藤井 聡 | 京都大学大学院工学研究科教授 |
|---|---|---|
| 委員 | 唐木 清志 | 筑波大学人間系教授 |
| 勝山 潔 | 一般社団法人日本民営鉄道協会常務理事 | |
| 桐谷 正信 | 埼玉大学教育学部教授 | |
| 清水 充 | 国土交通省総合政策局環境政策課長 | |
| 高橋 良則 | 公益社団法人日本バス協会常務理事 | |
| 谷口 綾子 | 筑波大学システム情報系教授 | |
| 寺本 潔 | 名桜大学国際学部国際観光産業学科特任教授 | |
| 松村 暢彦 | 愛媛大学大学院理工学研究科教授 | |
山﨑 雅生 |
国土交通省総合政策局参事官(交通産業)室参事官 |
(令和7年3月現在)